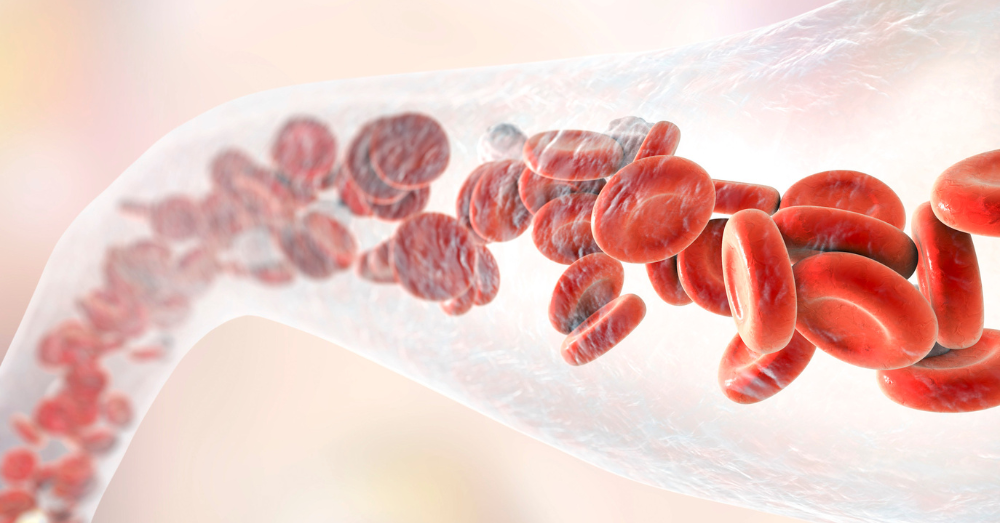卵巣嚢腫を発症した女性の中には、抜け毛を併発する方もいます。卵巣嚢腫が抜け毛に与える影響について気になる方もいらっしゃるでしょう。
女性にとって抜け毛は大きな悩みの一つであり、抜け毛の原因はさまざまです。
本記事では、卵巣嚢腫の症状や原因、抜け毛との関係性を解説します。
女性ホルモンの乱れや生理不順が抜け毛にどのような影響を与えるかも詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。
※本記事は日本皮膚科学会ガイドライン「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版」を参考に作成しています。
卵巣嚢腫(のう腫)について|種類や子宮筋腫との違いを解説

卵巣嚢腫(のう腫)とは、卵巣にできた袋状の良性腫瘍です。できたばかりの頃はほとんど症状を認めず、腫瘍が増大するとともに症状が出現します。
卵巣嚢腫は4種類に分類されます。
- 成熟奇形腫(皮様嚢腫)
- 漿液(しょうえき)性嚢腫(のう腫)
- 粘液性嚢腫(のう腫)
- 子宮内膜症性卵巣嚢腫(チョコレート嚢胞)
それぞれ好発年齢が異なり、若年者から60歳代まで幅広い年齢層で発症します。成熟奇形腫と子宮内膜症性卵巣嚢腫(のう腫)は、加齢とともに癌化のリスクが上がるため、卵巣嚢腫の診断はまず婦人科を受診しましょう。
卵巣嚢腫の他に、婦人科領域にできる良性腫瘍に子宮筋腫があります。30歳以上の女性20%〜30%に見られるため、聞いたことがあるかもしれません。どちらもたいてい良性腫瘍ですが、症状や発生部位(卵巣か子宮)が異なります。子宮筋腫の症状や治療方法については専門医へご相談ください。
参照元:日本産婦人科学会「子宮筋腫」
卵巣嚢腫の症状
卵巣嚢腫の発症初期はあまり症状がなく、腫瘍が大きくなるとともに症状が現れます。
小さいうちは日常生活に支障はなく、月経も多くの場合順調です。妊娠にもあまり影響しません。そのため、卵巣嚢腫は検診や腹痛の検査などで偶然見つかることも多いです。
腫瘍が大きくなると直径20cmを超えることもあり、大きくなるにつれて、膀胱や直腸など周囲の臓器を圧迫します。その際にあらわれる症状は、以下の4通りです。
- 頻尿
- 便秘
- 下腹部の違和感
- 月経異常
このほかに、大きくなった腫瘍が捻れたり破裂すると、急激な腹痛が現れます。場合により緊急手術となります。
卵巣嚢腫の診断方法
卵巣嚢腫の診断方法は3つです。
- 外診・内診
- 画像検査(経膣超音波・MRI・CT)
- 採血(癌があるかどうかの目安になる腫瘍マーカー測定)
診断は最初に外診と内診、超音波検査を行います。
経膣超音波検査は膣から機械を挿入して直接卵巣の形態を観察できるため、小さな腫瘍も見つけやすく、嚢胞の成分まで観察ができます。
さらに詳しい検査が必要な場合は、MRI検査や腫瘍マーカーを測定します。これらの検査結果をふまえて卵巣嚢腫が診断されます。
卵巣嚢腫の治療方法
卵巣嚢腫の多くは手術療法が選択されますが、一部ホルモン療法を行う場合もあります。無症状の場合や腫瘍が小さい場合、変化がないか定期的に経過を観察をします。
手術療法を考慮する目安は次の4つです。
- 大きさが5cm以上で捻転の恐れがある
- 腫瘍が増大傾向にある
- 自覚症状がある
- 将来悪性化の可能性がある、悪性が否定できない
腫瘍の大きさ・年齢・妊娠の希望などにより、治療方法や手術の術式が決まります。
参照元:日本婦人科腫瘍学会「卵巣嚢腫」
卵巣嚢腫になりやすい人の特徴

卵巣嚢腫のうち、子宮内膜症性卵巣嚢腫以外は原因がはっきりとわかっていません。子宮内膜症性卵巣嚢腫になりやすい人の特徴は次の表の通りです。
| 妊娠歴 | 妊娠経験がない女性に卵巣嚢腫が発生しやすい |
| 女性ホルモン | 女性ホルモンのうちエストロゲン分泌によってリスクが高くなる |
| 食事 | 高脂肪食によってエストロゲン分泌が促進し、発症リスクが高くなる |
卵巣嚢腫は自覚症状がほとんどありません。治療には早期発見が大切なため、定期的な婦人科検診を受診してください。
卵巣嚢腫と抜け毛の関係について

卵巣嚢腫と抜け毛には直接的な関係はありません。
しかし、卵巣嚢腫を治療する際のホルモン療法や手術による副作用で女性ホルモンが減少(閉経後と同じ状態まで減少)し、抜け毛につながることもあります。女性ホルモンのエストロゲンは、髪の毛の成長期を延長する役割があるためです。
また、卵巣嚢腫の症状によるストレスが間接的な原因として抜け毛を引き起こす場合もあります。抜け毛の原因によっては医療機関での治療が必要な場合もあるため、AGA治療専門のクリニックへ相談がおすすめです。
卵巣嚢腫にともない抜け毛を引き起こしやすい人の特徴

卵巣嚢腫にともない抜け毛に引き起こしやすい人の特徴は3つです。
- 女性ホルモンのバランスが乱れている
- ストレスを溜め込んでいる
- 老化・更年期症状が進んでいる
女性ホルモンのバランスが乱れている
卵巣嚢腫にともなう女性ホルモンバランスの乱れが原因で、抜け毛を引き起こす可能性があります。卵巣嚢腫を治療する際、副作用により女性ホルモンの分泌が減少します。これにより見られる症状は2つです。
- 抜け毛が起こりやすい
- 更年期と同一の症状が出る
ホルモンバランスの乱れが原因で起こる「生理不順」「無月経」の場合にも、髪の毛の成長に必要な女性ホルモンの分泌が減少するため、抜け毛が起こりやすくなります。
ストレスを溜め込んでいる
卵巣嚢腫によるストレスも、抜け毛を引き起こしやすい要因の1つです。女性のホルモンバランスは非常に繊細なため、ストレスなどの異常が生じた場合には、ホルモンバランスが乱れやすくなります。ストレスは自律神経を乱し、血流の悪化や睡眠不足を招くため、抜け毛が増えるリスクも増加します。
関連記事:女性の抜け毛とストレスの関係性について解説|女性に多い脱毛症の原因も紹介
老化・更年期症状が進んでいる
卵巣嚢腫の手術療法にともなう副作用として、老化や更年期症状が進むことも抜け毛を引き起こしやすい要因の1つです。
閉経前の女性が卵巣を摘出すると、女性ホルモンの分泌量が減少し老化や更年期症状が進むこともあります。女性ホルモンの分泌量が減少すると、髪の毛の成長に必要な「エストロゲン」の減少によりヘアサイクルが短縮し抜け毛が増えます。
更年期症状が進むと不安やイライラした気分が強くなり、些細なことでストレスが溜まりやすくなります。ストレスを溜め込むと自律神経が乱れ、血行不良も起きやすく抜け毛が増えるリスクも増加するでしょう。
卵巣嚢腫の症状以外にチェックしたい抜け毛の原因

卵巣嚢腫の症状以外にチェックしたい、女性に起こる抜け毛の原因は5つです。
- FAGA(女性型脱毛)
- びまん性脱毛症
- 壮年性脱毛症
- 牽引性脱毛症
- 生活習慣の乱れ
FAGA(女性型脱毛)
FAGA(女性型男性型脱毛症|Female Androgenetic Alopecia)は更年期の女性に多い脱毛症で、頭頂部の広い範囲で髪の毛が薄くなります。
男性型脱毛症と同じように特定のパターンをもっていますが、前髪は残り頭頂から前頭部にかけて薄毛となるのが男性と異なる点です。
女性の抜け毛はホルモンだけでは説明できないケースも多いため、近年では世界的にFPHL(Female Pattern Hair Loss)と呼ばれています。
卵巣嚢腫を治療する際のホルモン補充療法や薬剤による脱毛は、こちらからは除外されます。
FAGAの治療方法については専門医へご相談ください。
参照元:男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版
関連記事:女性の薄毛(FPHL、FAGA)はなぜ起こる? 問題点・原因・特徴・効果的治療法を解説
びまん性脱毛症
びまん性脱毛は幅広い年齢層の女性に見られる脱毛症の一つです。
主な原因は加齢による女性ホルモンの減少ですが、ストレスや生活習慣の乱れなども原因となります。
髪の毛全体のボリュームが減少し地肌が透けて見えるように脱毛しますが、男性のように局所が禿げ上がることはほとんどありません。
びまん性脱毛症の治療方法については専門医へご相談ください。
壮年性脱毛症
女性の壮年性脱毛症は、女性ホルモンの減少にともない頭髪の薄毛や抜け毛が進行する脱毛症です。
症状は頭頂部に強く、男性型脱毛症のように前頭部や生え際の髪の毛が薄くなることはありません。
ホルモンバランスの変化やストレス・乱れた生活習慣・遺伝的な要因により発症リスクが増加すると考えられています。
壮年性脱毛症の治療方法については専門医へご相談ください。
参照元:男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版
牽引性脱毛症
牽引性脱毛症は、髪の毛を引っ張ることにより発症する脱毛症です。同じ髪型を長く続けると、局所の毛根や頭皮にダメージが加わり抜け毛を引き起こしやすくなります。
一過性の脱毛症のため、初期の段階であれば引っ張る行為をやめると元に戻ります。
しかし、ダメージが毛包にまでおよんだ場合には、髪の毛が生えなくなる可能性もあるため注意が必要です。
牽引性脱毛症の治療方法については専門医へご相談ください。
参照元:日本皮膚科学会「皮膚科Q&A」
生活習慣の乱れ
生活習慣の乱れも、卵巣嚢腫以外に考えられる抜け毛の原因の1つです。睡眠不足が続くと睡眠中の成長ホルモンの分泌量が減少し、髪の毛の成長を妨げます。
また過度なダイエットにともなう栄養不足は、髪の毛の成長に必要な栄養素が不足し抜け毛のリスクが増加するため注意が必要です。
卵巣嚢腫にともなう抜け毛が気になる時の改善策

卵巣嚢腫にともなう抜け毛が気になるときの改善策を5つ紹介します。
- AGA治療専門のクリニックへ相談する
- 栄養バランスの良い食事を摂る
- 軽い運動でストレス発散と心身の健康を目指す
- 自分に合った十分な睡眠時間を確保する
- 髪の毛や頭皮にやさしい髪型やヘアケアを行う
AGA治療専門のクリニックへ相談する
卵巣嚢腫にともなう抜け毛が気になる場合は、AGA治療専門のクリニックへ相談をおすすめします。
AGA治療専門のクリニックでは、髪の毛の状態を詳しく調べ抜け毛の原因を突き止めます。個人の状況に合わせた適切な治療法の提案ができ悩みについて適切なアドバイスが可能です。
悩みの原因によっては医療機関での治療が必要な場合もあるため、専門医へ相談を検討してください。
栄養バランスの良い食事を摂る
卵巣嚢腫にともなう抜け毛が気になるときは、髪の毛の成長促進が見込めるバランスの良い食事を摂取しましょう。髪の毛の育毛効果が期待できる栄養素は次の6通りです。
| 栄養素 | 髪の毛に対して期待できる主な効果 |
| タンパク質 | 三大栄養素の1つで、髪の毛を作る原料 |
| コラーゲン | 毛母細胞に栄養や酸素を送り届け、毛乳頭細胞の増殖を促す |
| 亜鉛 | 体内のアミノ酸を、髪の毛の原料となるケラチンへと再合成するはたらきがある |
| ビタミンA、B、E | 髪の毛の成長促進や、良好な頭皮環境の維持に欠かせない成分 |
| ヨウ素 | 新陳代謝を活発化させ、髪の毛の成長をサポート |
| イソフラボン | 女性ホルモンのエストロゲンに似た役目があり、髪の毛や肌にハリとうるおいを与える |
関連記事:【女性に聞く】薄毛が改善した食べ物7選|髪の毛を増やすためには何を食べるべき?
軽い運動でストレス発散と心身の健康を目指す
軽い運動でストレス発散と心身の健康を目指すことも、卵巣嚢腫にともなう抜け毛が気になるときにおすすめです。
適度なウォーキングやストレッチはストレス発散や血行促進を助け、髪の毛の成長に必要な栄養素が頭皮へ届きやすくなります。また自律神経のバランスも整いやすくなり、心身の健康にもつながります。
自分に合った十分な睡眠時間を確保する
自分にあった十分な睡眠時間の確保も、卵巣嚢腫にともなう抜け毛が気になるときにおすすめです。
睡眠不足によって成長ホルモンの分泌が減少すると、髪の毛の成長や頭皮の新陳代謝に悪い影響を与えます。
成長ホルモンは、深い眠りについたときに多く分泌されるため、睡眠の質を高めるように工夫しましょう。
就寝前はスマホやパソコンの使用を避けるなど刺激を減らし、自分に合ったリラックス方法を取り入れてみてください。
髪の毛や頭皮にやさしい髪型やヘアケアを行う
卵巣嚢腫にともなう抜け毛が気になるときは、髪の毛や頭皮にやさしい髪型やヘアケアを行いましょう。
ヘアピンやヘアゴムなどできつく髪の毛を縛ったり留めたりすると、頭皮に負担がかかり、抜け毛につながる可能性があります。髪の毛を結わない日をつくることや、ゆるくまとめる髪型がおすすめです。
ヘッドスパや頭皮マッサージなどのヘアケアも、頭皮環境を整えるのにおすすめです。また、血行促進やリラックス効果により、薄毛予防に期待できます。
卵巣嚢腫の治療に支障が出る抜け毛対策はしないように注意

卵巣嚢腫の治療に支障が出る抜け毛対策はしないよう、次の3点に注意してください。
- 個人的に抜け毛治療の薬を購入して服用
- 過度な運動
- 過度な心配
抜け毛治療の薬は卵巣嚢腫の治療と相互作用を起こす可能性があるため、医師に相談せずに服用することは避けてください。また、治療の妨げになるほどの運動、卵巣嚢腫への過度な心配も、ストレスの原因となるため注意しましょう。
卵巣嚢腫に伴う抜け毛でお困りの方はベアAGAクリニックへご相談ください

卵巣嚢腫に伴う抜け毛でお困りの方はベアAGAクリニックへご相談ください。
卵巣嚢腫と抜け毛には直接的な関係がありません。しかし、卵巣嚢腫を治療する際の副作用により、女性ホルモンが減少し、抜け毛につながることがあります。
卵巣嚢腫の診断や治療は、まず婦人科を受診しましょう。そして抜け毛に対するお悩みは、医療機関での治療が必要な場合もあるため、AGA治療専門のクリニックへご相談ください。
ベアAGAクリニックでは1万人以上の治療実績を持つ院長が自ら診察を行い、一人ひとりに合った治療法を提案します。カウンセリングは無料のため、髪の毛の成長に不安や疑問がある方は気軽にお問い合わせください。
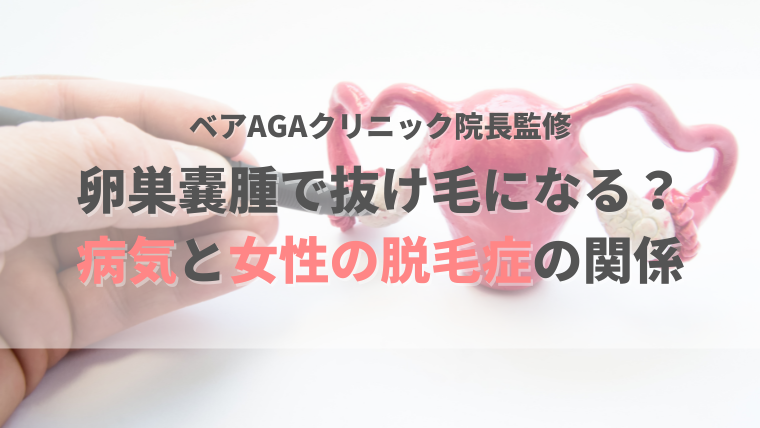








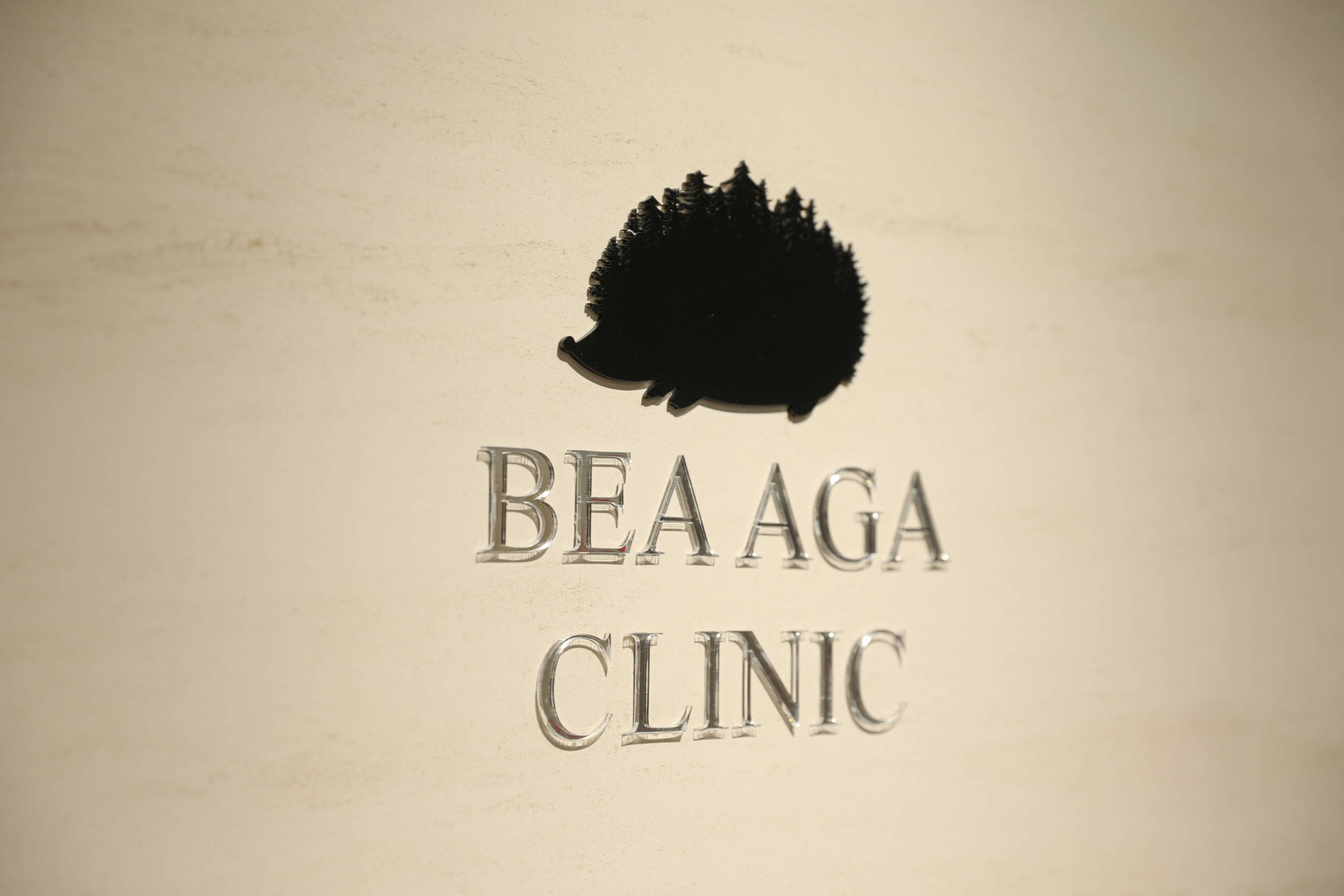 こめかみの薄毛は、多くの女性にとって大きな悩みですが、適切な対策を講じることで改善することが可能です。 まずは、薄毛の原因を特定し、ホルモンバランスの整備や栄養バランスの改善、ストレス管理を行うことが重要です。 育毛剤やサプリメントの使用も効果的な方法です。また、専門医による診断と治療を受けることで、効果的に薄毛を改善することができます。 健康な髪を取り戻すために、日常生活の中でできることから始めてみましょう。 こめかみの髪の毛(サイド)が薄くてお悩みの女性はベアAGAクリニックまでお気軽にご相談下さい。
こめかみの薄毛は、多くの女性にとって大きな悩みですが、適切な対策を講じることで改善することが可能です。 まずは、薄毛の原因を特定し、ホルモンバランスの整備や栄養バランスの改善、ストレス管理を行うことが重要です。 育毛剤やサプリメントの使用も効果的な方法です。また、専門医による診断と治療を受けることで、効果的に薄毛を改善することができます。 健康な髪を取り戻すために、日常生活の中でできることから始めてみましょう。 こめかみの髪の毛(サイド)が薄くてお悩みの女性はベアAGAクリニックまでお気軽にご相談下さい。







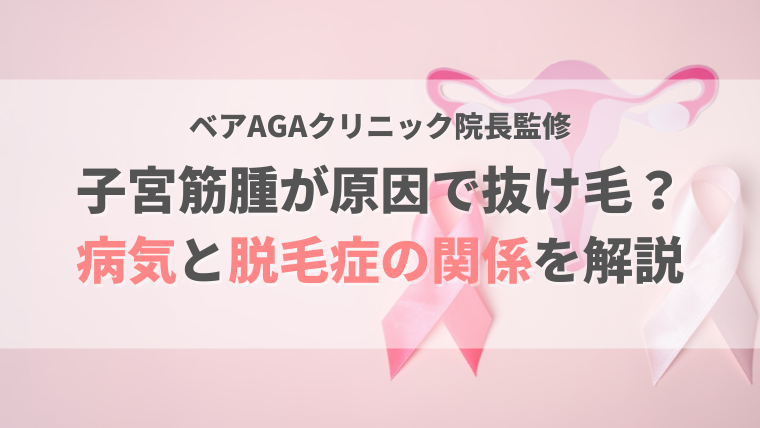

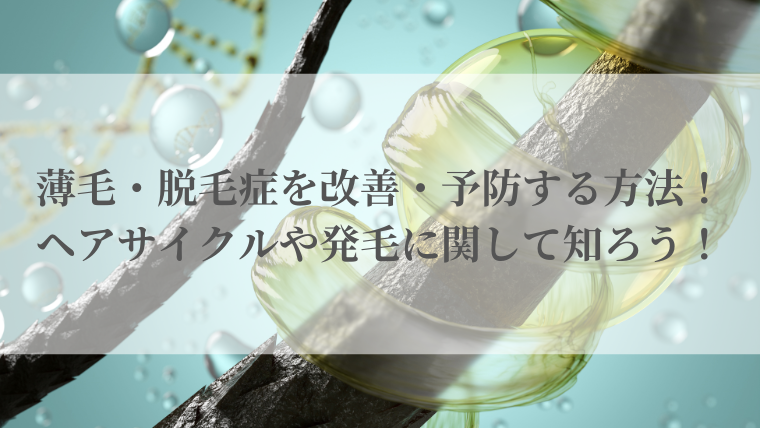
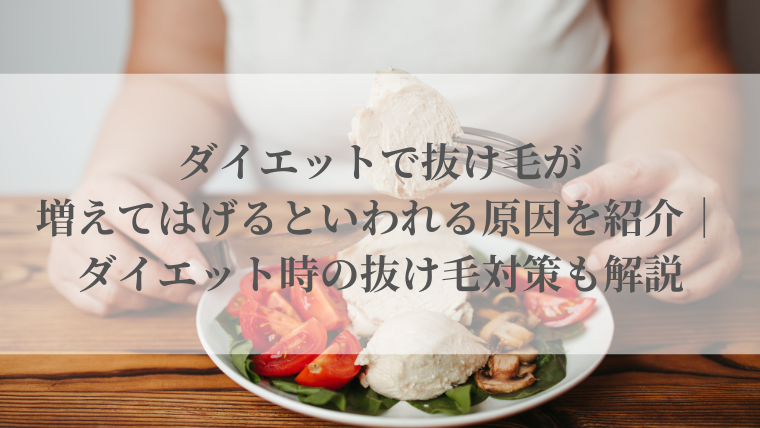


















 髪の健康を維持するためには、ビタミンが不可欠です。ビタミンは細胞の生成や修復、栄養の吸収を助ける働きを持ち、髪の毛にも大きな影響を与えます。 特に、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンEは髪の健康に重要な役割を果たします。 ビタミンを適切に摂取することで、髪の成長を促進し、抜け毛や薄毛を予防することができます。
髪の健康を維持するためには、ビタミンが不可欠です。ビタミンは細胞の生成や修復、栄養の吸収を助ける働きを持ち、髪の毛にも大きな影響を与えます。 特に、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンEは髪の健康に重要な役割を果たします。 ビタミンを適切に摂取することで、髪の成長を促進し、抜け毛や薄毛を予防することができます。